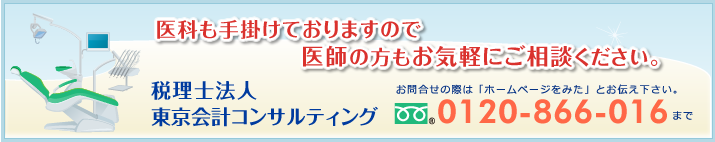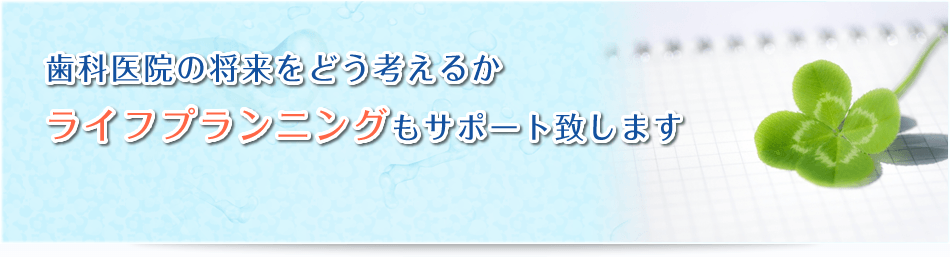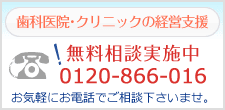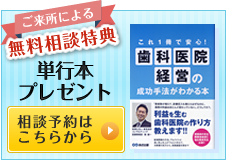歯科医の相続・事業継承
あなたはどちらにしますか?
- 後継者を育てる
- 集患について考える
- 設備を見直す
- リタイア後の必要資金を考える
- 院長・スタッフの高齢化
- 患者の高齢化
- 設備の老朽化
- 収入減少による資金不足
医院を開業されている先生方は、
現在の医院を将来的にどのように続けていけばよいか、
ということを一度はお考えになったことがあるのではないでしょうか?
診療報酬のマイナス改定の報道を耳にしたり、先生ご自身の体力の限界を時折感じた瞬間に『将来どうしようか…』と頭をよぎることがあるとおっしゃる先生も珍しくありません。
事業承継は直ぐにできるものではありません。
近頃では「出口戦略」などとも言われているように、診療所の引き継ぎに際しての作戦が必要なのです。
そのため、医院の将来設計・相続・事業承継などについては、
今から少しずつ考えていくことをお勧めしております。
事業承継の形態
個人開業医の場合| ① | 親族に承継する |
|---|---|
| ② | 従業員等に承継する |
| ③ | 第三者に譲渡する |
| (④ | 廃業する) |
(医療法人の場合には「他の医療法人と合併する」という形態も存在します)
個人開業医の場合、相続が発生した時の事業承継は「後継者」がいるかいないかで、
その手続方法は違ってきます。
| 後継者がいる |
|
|---|
さらに、相続が発生した場合を考えてみましょう。
これまで先生個人の名義となっていた医院の土地、建物、医療機器などの事業用財産はその一つひとつが相続財産を構成することになります。
このときご子息ご令嬢などの後継者が引き継いでくれるようであれば、さほど問題は生じないかもしれません。
後継者がいない場合、歯科医師または医師の資格のない人が事業用財産を相続することも考えられます。このような場合には、せっかく先生が築き上げてきた診療所がもはや運営不可能な状態になってしまう恐れが大きいのです。
永続的な医療の継続という社会的使命に応えるためにも、
「事前に診療所をどう引き継ぐかを考えておくことの重要性」をご理解いただけると思います。
個人医院の相続対策
税務上の観点からすると、
相続・事業承継をスムーズに進めようとする場合には、医療法人化はオススメです。
「出資持分の定めのない社団医療法人または財団法人」の場合、
設立時に「拠出した財産」は拠出者(個人開業医)から医療法人への財産の贈与になります。
医療法人への財産の贈与とはどういうことか?ですが、
先生が所有していた医院の建物や土地、医療機器などを医療法人のものにしてしまうということです。
まだ???ですよね。
通常の株式などの場合と比べてみると、いくらか分かりやすくなると思います。
株式会社に100万円出資をすると、100万円分の株式を取得します。
上場企業などの場合、この株式を市場で売却すれば出資額を回収することができます
(当然、100万円を上回ることもあれば、下回ることもあると思いますが…)。
この株式を医療法人の場合には「持分」と呼んでいます。
では、上の文章の一部置き換えてみましょう。
医療法人に100万円出資をすると、100万円分の持分を取得します。
この持分がもらえる医療法人を「出資持分の定めのある社団医療法人」と呼んでいます。
さらに文章の一部を置き換えてみましょう。
医療法人に100万円贈与をすると、持分を取得できない
これが「出資持分の定めのない社団医療法人」の所以です。
出資持分がないということは、相続財産を構成しない、ということにつながります。
すなわち、相続税の課税財産に含まれずに済むのです!
先生個人の持ち物のままで相続が発生すると医院の土地や建物、医療機器は相続財産構成する。
これに対し、医療法人を設立し、医療法人に拠出された医院の土地や建物、
医療機器は相続財産を構成しない。
これはかなりの相続対策になると思いませんか?